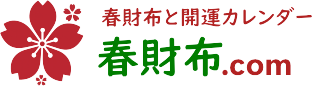不成就日とは、で調べると…
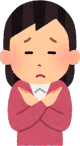
何事も成就しない日。
そもそも、事を起こすのがダメで、何をやっても良くない結果を招く
みたいに説明されているので「そんな良くない日があるのか」と、気になっちゃいますよね。
この記事では、不成就日の一覧から始めて、その由来や意味などを深堀りしています。
不成就日の元々の使われ方に沿った過ごし方や、また、何か事を起こしてしまった時に、気にしないようにする考え方なども紹介してるので、不成就日に何かをしてしまって、気になる方は、参考にしてみて下さいね。
2026年(令和8年)の不成就日 一覧
では、まずは、2026年(令和8年)の不成就日の全一覧表です。
不成就日が、いつかを調べたい方は、ご活用下さい。
三隣亡や受死日などの凶日と不成就日が重なる場合、それも、もわかるようになっています。
六曜では、大安と重なる不成就日はありますが、仏滅と重なる不成就日はありません。
また、建築、引っ越し、旅行などにいいとされる大明日と重なる不成就日や、何事を始めるのに良いとされる一粒万倍日と重なる不成就日も結構あります。
2026年1月の不成就日
- 1月1日(日)不成就日 大安 元日
- 1月9日(金)不成就日 先勝
- 1月17日(土)不成就日 先負 一粒万倍日
- 1月24日(土)不成就日 大安
2026年2月の不成就日
- 2月1日(日)不成就日 先勝 三隣亡 大明日
- 2月9日(月)不成就日 先負
- 2月19日(木)不成就日 先負
- 2月27日(金)不成就日 大安 大明日
2026年3月の不成就日
- 3月7日(土)不成就日 先勝 受死日
- 3月15日(日)不成就日 先負
- 3月20日(金)不成就日 先負 巳の日 春分の日
- 3月28(土)不成就日 大安
2026年4月の不成就日
- 4月5(日)不成就日 先勝 大明日
- 4月13日(月)不成就日 先負 巳の日
- 4月17日(金)不成就日 先負 新月 大明日
- 4月25日(土)不成就日 大安 己巳の日 大明日
2026年5月の不成就日
- 5月3日(日)不成就日 先勝 大明日
- 5月11日(月)不成就日 先負
- 5月20日(水)不成就日 先負 天赦日
- 5月28日(木)不成就日 大安 寅の日 大明日
2026年6月の不成就日
- 6月5日(金)不成就日 大安 大明日
- 6月13日(土)不成就日 先勝 一粒万倍日 大明日
- 6月19日(金)不成就日 先負 甲子の日 受死日
- 6月27日(土)不成就日 大安 大明日
2026年7月の不成就日
- 7月5日(日)不成就日 先勝
- 7月13日(月)不成就日 先負
- 7月19日(日)不成就日 大安 天赦日 一粒万倍日 受死日
- 7月27日(月)不成就日 先勝 寅の日 大明日
2026年8月の不成就日
- 8月4日(火)不成就日 先負 大明日
- 8月12日(水)不成就日 大安 大明日
- 8月15日(土)不成就日 先負 大明日
- 8月23日(日)不成就日 大安 己巳の日 大明日
2026年9月の不成就日
- 9月8日(火)不成就日 先負
- 9月12日(土)不成就日 先負
- 9月20日(日)不成就日 大安
- 9月28日(月)不成就日 先勝 巳の日 大明日 受死日
2026年10月の不成就日
- 10月6日(火)不成就日 先負
- 10月11日(日)不成就日 先負 一粒万倍日 大明日 新月 三隣亡
- 10月19日(月)不成就日 大安 寅の日 受死日
- 10月27日(火)不成就日 先勝
2026年11月の不成就日
- 11月4日(水)不成就日 先負 一粒万倍日 大明日 三隣亡
- 11月12日(木)不成就日 先勝 寅の日
- 11月20日(金)不成就日 先負 一粒万倍日
- 11月28日(土)不成就日 大安 大明日
2026年12月の不成就日
- 12月6日(日)不成就日 先勝 寅の日
- 12月13日(日)不成就日 先負 大明日
- 12月21日(月)不成就日 大安 己巳の日 大明日
- 12月29日(火)不成就日 先勝 大明日
不成就日の由来
不成就日は、本当なのか、迷信なのか、気にした方がいいのか、気にしなくてもいいのか、それを考える前に、まずは、不成就日の由来を見てみましょう。
そもそも、不成就日は、いつ、誰が作って広めたのでしょうか。
日本で古くから使われていた暦には、年月日以外にも、
- その日が運のいい日なのか、悪い日なのか、や
- その日の時間や方位の吉凶
などを占う項目が載っていました。
これを暦注(れきちゅう)と言います。
暦注には、大安や仏滅で有名な六曜や、寅の日、巳の日などで知られる干支を始め、様々な項目が掲載されていました。
それで数ある暦の暦注の1つには、選日(せんじつ)という項目があり、不成就日は、その選日の中の日として分類されています。
選日は、全部で8種類あります。
- 八専(はっせん)
- 十方暮(じっぽうぐれ)
- 不成就日(ふじょうじゅび、ふじょうじゅにち)
- 天一天上(てんいちじん、てんいつじん)
- 三隣亡(さんりんぼう)
- 三伏(さんぷく)
- 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
- 犯土(つち、ぼんど)
- 臘日(ろうにち、ろうじつ)
日本の暦事情(平安時代~江戸時代)
日本の暦は、862年2月3日(平安時代)~1685年2月3日(江戸時代)までは、中国歴の1つの宣明暦(せんみょうれき)が使われていました。
その後、改暦が行われ、1685年2月4日~1755年2月10日までは、渋川春海によって編纂された初めての和暦である貞享暦(じょうきょうれき)が使われています。
各地で出版された暦本
江戸時代には、幕府公認の暦から、神社や、地方の藩が独自に編纂した暦まで、さまざまなものが出版されていました。
では、不成就日も、当時、出版されていたどの暦にも載っていたかというと、そんなことはなく、実際は、ほとんどの暦には載っていなかったようです。
不成就日が暦に載っていたのが確認されているのは、会津藩が出版していた会津暦。
会津暦(あいずこよみ)は、会津若松の諏訪神社の神官によって作られ、幕府の許可を得て出版していた地方暦の1つです。
さらに、会津暦に不成就日が載っていたのは、宣明暦(せんみょうれき)時代のことのようで、1865年に、貞享暦(じょうきょうれき)に改暦されてからは、不成就日の記載が見当たらなくなっています。
参考資料
会津暦のデジタルコレクション(国立国会図書館)
不成就日は、そんなに気にしていなかった?
不成就日は、現代の暦本や運勢暦には、ほとんど、掲載されているのですが、当時は、会津暦にしか掲載されていなかったところをみると、実は、あまり、気にされていなかった日なのかもしれません。
ところが、人の世の常として、気になるのは、運勢がすごくいい日か、運勢がすごく悪い日です。
現代まで伝えられ、知名度が高くなっている日も、大開運日か、大凶日の割合が多いですからね。
不成就日も幕府公認の暦では、会津暦にしか掲載されていなかったものの、密かに民間の暦には掲載され続け、それが、ついには、現代まで伝わり、今、発売されている市販の暦本やカレンダーへの掲載に繋がってるんじゃないか、と考えられます。
不成就日にしてはいけないこと(現代の暦本での意味)
現代の市販の暦本に掲載されている不成就日の意味をみてみると「この日は、何をやっても不首尾の結果を招く凶日」と書かれています。
願い事をしたり、急に思い立ったことを始めたり、何かことを起こしたりするには向いてない日で、以下のようなことも「やってはならない」こととして挙げられています。
- 結婚式をする
- 開店する
- 赤ちゃんに名前をつける
- 引っ越する
- 契約する
- 相談する
- 使用人を雇用する
- 柱立てをする
- 造作する
造作は、何かを建築したり、改築したりする…というような意味です。
現代では「不成就日は、ほとんど、何をするにも良くない日」というような捉え方が一般的で、ウィキペディアにも、以下のように書かれています。
何事も成就しない日とされ、結婚・開店・子供の命名・移転・契約・芸事始め・願い事など、事を起こすことが凶とされる。市販の暦では他にも色々なことが凶となっていて、結局は全てのことが凶ということになる。
ウィキペディアの不成就日 より
不成就日は気にしない
さて、ここまで見てきたように、不成就日の由来や、その起源から考えてみると…
不成就日は、公式の暦には乗るような日ではなかったものの、大凶日であるがゆえに、民間の暦には、密かに載り、現代まで伝わっている
というようにも言えそうです。
不成就日は、月の十二支と、日の十二支、さらには、五行の組み合わせをもとに、約8日ごとにやって来ますが「何かをすると、悪い結果に終わる」というような統計的なデータがあるわけではありません。
ある法則で決めた占い的な吉凶ですので、別の法則で決めている、例えば、有名な六曜で見れば、不成就日が、縁起のいい大安にあたっている、ということも有り得るわけです。
そもそも、暦の吉凶占いは、その種類によって、同じ日が、縁起のいい日だったり、悪い日だったりします。
占星術でみれば、今日はいい日だけれど、九星気学でみれば、今日は良くない日、と出るのと同じようなものですね。
そもそも、願い事が叶わない日や、何をやっても上手くいかない日が、全員一斉にやってくる…というのもおかしな話です。
なので、ここまでの説明を読んで、
「不成就日は、迷信だし、意味ないので、気にしなくてもいいな」
と、感じられた方は、不成就日を、特に意識をせず、普通に過ごしても大丈夫だと思います。
「そうは言っても、やっぱり、ちょっと気になるんだよねぇ」
という方は、以下に、不成就日の上手な活用方法や、うっかり事を起こしてしまった時の考え方などを書きましたので、こちらをご覧下さい。
不成就日の過ごし方
不成就日に、科学的根拠はない、と言われても、なんか、気になってしまう場合には、その心の動きの方で、良くない結果を招いてしまう場合もあるので、基本は、静かに過ごすのがおすすめです。
また、不成就日の元々の使われ方を探ると、以下のような活用方法もあります。
不成就日にやっていいこと
不成就日を意識していた時代には、まだ、今のような月曜日~日曜日のような七曜日はありませんでした。
そのため、約8日ごとにやって来る不成就日を休みにして、どうも、休日として活用していた節もあります。
何やってもダメな日なので、いっそのこと、お休みにしてしまおう…っていうわけですね。
なので、この使われ方を採用すれば、不成就日には、休息をとって、ゆっくり休む、というような活用方法も考えられます。
不成就日にしてはいけないことをしてしまった
すでに、何かの行動をしてしまったものの、不成就日のことを、後から知って、気になる場合もありますよね。
ここでは、「何かをしてしまった時に、実はその日が不成就日だった」っていうことを、後から知った場合の考え方などをまとめました。
不成就日に財布を買ってしまった
不成就日に財布を買ってしまって気になるのは、金運が良くない財布になるんじゃないか、っていうことですよね。
その場合は、不成就日と同じ選日で、金運にいいとされる「一粒万倍日」にも財布を買ってみます。
お金を使いたくないようなら、100円ショップに売っているような財布でもいいです。
一粒万倍日は、一粒を万倍にも増やしてくれる日ですので、100円の財布でも、100万円が入ってくるような財布に育つ筈です。
もしも、本当に、100万円が入ってくるような財布に育ったら、それを元手に、また、一粒万倍日に、メインで使う財布を買い直します。
一粒万倍日に買った財布でも、特に、お金が入って来るような様子がなければ、一粒万倍日も当たらないのだから、不成就日も気にしなくていい、と考えます。
不成就日に入籍や結婚をしてしまった
不成就日は、約8日に一回やって来ます。
なので、入籍日や結婚式のお日柄などを気にしないカップルなら、知らず知らずのうちに、不成就日に、入籍や結婚をしてしまっていることが多々あると思います。
とは言え、不成就日に結婚したから、あの夫婦は、離婚してしまった…というような話は、特に、広まっていません。
もしも、本当に、不成就日に結婚した夫婦が不幸になるなら、その話が、もっと広まってるはず…と考え、気にしないようにします。
不成就日に引っ越しした
自分だけで引っ越しするなら別ですが、引っ越し業者に頼む場合は、自分の都合と、業者の都合を合わせて日取りを決めるので、引っ越しする日を、そんなに、自由に選べるわけではないですよね。
なので、引っ越しの日が、不成就日になることも、けっこうあるかと思います。
もしも、引っ越しの日が、不成就日だった場合は、まずは、その日が、ほかの吉日と重なってないか確認してみて下さい。
このページの不成就日の一覧表からもチェックできます。
チェックしてみると、大安はもちろん、建築、移転、旅行には大吉日といわれる大明日(だいみょうにち)と重なってることが、けっこうあります。
もしも、吉日と重なっていれば、吉日が打ち消す、と考えて、引っ越しの日が不成就日にあたることは気にしないようにします。
打ち消すとは考えられなかったり、やっぱり、どうしても気になってしまうようだったら、引越し先の最寄りの神社に、お参りに行って、お守りを買ったり、ご祈祷や、お祓いをしてもらったり、とにかく、自分の気持ちがリセットされそうなことを試してみます。
不成就日に宝くじを買った
年末ジャンボや、サマージャンボなど、高額の宝くじが当たる確率は、1000万分の1とか、500万分の1とかです。
一方で、金運にいいとされている一粒万倍日や、寅の日に、宝くじを買っている人も、たくさんいる筈です。
しかしながら、その人たち全員の宝くじが当たるわけではありません。
なので、宝くじを買った日が、不成就日だったとしても、気にしないようにします。
どうしても、気になるようなら、一粒万倍日に、もう一枚だけ、高くじを買ってみます。
もしも、当たれば、一粒万倍日のおかげですし、当たらなければ、今後は、気にしないようにしよう…と思えます。
不成就日に買い物をした
不成就日は、日常的な買い物をしてはいけない、というようなことにはなってないので、普通の買い物をするのは、問題ないと思います。
不成就日に神社へ行った
神社へ行くのは、何か事を起こしたりするわけではないので、不成就日に行ったとしても、特に、問題はありません。
とは言え、「不成就日の願い事は叶わない」となっているので、神社へ願い事をした場合は、気になるとは思います。
ただ、もしも、本当に、神社へ行くことと、不成就日が関係あるようでしたら、神社の方で、そのことを謳っている筈です。
ところが、神社で、厄年のお祓いなどは見かけることはあっても「不成就日のお願い事は叶いません」というようなことは見かけません。
そもそも、神様は、開運日のお願いだから、願いを叶えてあげたり、不成就日の願い事だから、願いを叶えなかったりはしない、と考えて気にしないようにします。